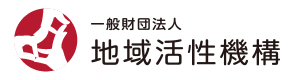“地元愛”に溢れる人々と協働しながらまちを再生
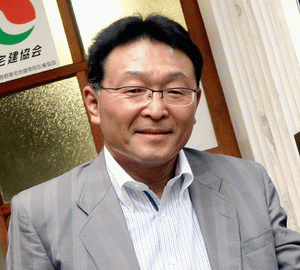
長野県飯田市
株式会社飯田まちづくりカンパニー
取締役事業部長 三石 秀樹 氏
株式会社飯田まちづくりカンパニーは民間が主導する第三セクターの会社である。飯田市の市街地には1974年に中央資本の大型店が進出したが、人口減少や郊外地域への人の流れの移行などが相まって、市街地は衰退の一途をたどる。これに危惧を抱いた商店主たちが行政とともに勉強会を発足させ、中心市街地の活性化をテーマに、再開発事業などを計画。この実施に向けて、市民・行政が一体となって同社が設立された。
主な取り組み
◎不動産販売・賃貸・管理などのディベロッパー事業
◎まちづくり調査、コンサルティング業務などの調査・研究開発事業
◎空き店舗の活用、土地の集約化などの市街地ミニ開発事業
◎物販・飲食事業物販の運営
◎商店街の集客イベント、商業塾の企画運営、文化事業
◎高齢者支援サービス、福祉関連ネットワークの形成などの福祉サービス事業
など
まちづくりの根幹は“地元愛”
――飯田はもともと城下町として発展したとお聞きしていますが。
三石:飯田城が築かれたのは古く13世紀のことですが、戦国時代の末頃に城下町の大規模整備がなされて、以降、三河と信州を結ぶ三州街道の物流拠点として大きな発展を遂げました。明治時代も、生糸や木材などの地場産業で栄えた経済都市で、信州一の商都と言われた時期もありました。農業の面でも、この地域は寒い土地で収穫される作物の南限、暖かい土地で収穫される作物の北限です。飯田のりんごはほかのどの地域のりんごよりも美味だと言う人もいるほどです。
――そのような飯田市も現在はさまざまな問題を抱え、三石さんはまちづくりの活動を担っていらっしゃいます。活動を始められたきっかけは、どのようなものでしたか。
三石:「丘の上」と称する中心市街地の衰退に関する勉強会でまちの人たちが再開発の話を聞いた時に、あるコンサルタントの方から、とにかく地元の資本、行政や企業、そして地元の人材をフル活用することが肝要だとアドバイスを受けました。
都会から大手のディベロッパーやゼネコンを呼び込んでも、それが本来の地域の地力を掘り起こすことにはならない場合がある。彼らが引き揚げると、地元に残るのはハコだけだと。
 飯田地域交流センター(りんご庁舎)
飯田地域交流センター(りんご庁舎)
――強烈な指摘ですね。
三石:ならば、自分たちで再開発のまちづくりを始めようという結論に達して、1998年に立ち上げたのが当社です。そろそろ20年ですが、初期の10年間はこのような事業を担える人材の確保に苦労しました。「何かいいことありそう」的な考えは論外としても、やはり根幹に“地元愛”がない人にはこの事業は担えません。
今、中心市街地でのイベントなどは高校生とコラボしています。高校生が地域人教育という授業の一環でイベント活動を手伝ったり、自分たちでショップを開いたり、ケーキ屋さんや和菓子屋さんとコラボして新商品をつくったりします。すると、親や先生としかしゃべらなかった彼らが、まちなかのおじさんやおばさんたちと言葉を交わすようになり、それまで知らなかった地元の問題に気づいたりします。これも“地元愛”の種まきの1つと考えていますし、結果も出てきています。
他の団体との協働のあり方
 飯田のシンボル・りんご並木通り
飯田のシンボル・りんご並木通り
――御社の事業の骨格についてお聞かせください。
三石:他の団体との協働も踏まえて、中心市街地のミニ開発事業、物販・飲食事業、イベント・文化事業、福祉サービス事業、これらが活動の柱になっています。
――中心市街地の再開発や活性化に向けては、どの地方でもさまざまな問題を抱えているようですが。
三石:ご指摘の“さまざまな問題”としては、閉鎖したままで貸し出さない店舗、つまり空き店舗の問題があります。これには2つのパターンがあり、1つは高度成長期にそれなりに収益を上げ、今現在は店舗を貸し出さなくても生活に支障がない元商業者の場合。もう1つは親が店舗を閉め、子どもたちが県外や都会に出たまま帰らない場合です。私たちが行っている働きかけは、経済産業省が言う「利用と所有の分離」という手法です。要するに、当社がオーナーから借り上げて別の人に貸し出す、というやり方です。飯田のまちのシンボル的通りであるりんご並木周辺の店舗は、ゼロに近いところまで落ち込んでいましたが、当社による再生事業の結果、多くの店舗が出店し、最近では「りんご並木横丁」という町屋再生事業も実施しています。
――他の団体との協働についてもお聞きできますか。
三石:支援しているのは、NPOが2団体、一般社団法人が1団体、市民団体が3団体です。そのうちの1つ、NPO法人いいだ応援ネット イデアは15年ほど活動していますが、5年前から定期的に「まちゼミ」という名称の商店街事業などを開催しています。当社は資金的にも人的にも支援しています。
また、市民団体・IIDA WAVEは「暮らして楽しい街、飯田」をコンセプトに若者たちが活動していますが、このような若者のなかからまちづくりを担える人材が輩出されています。
地方創生の鍵は人材の確保・育成
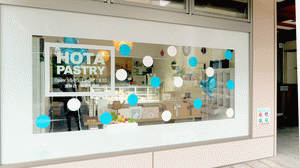
Uターンして頑張っているケーキ屋さん
――さまざまな可能性が育っているということですね。一方では、県外や都会に出た子どもたちが戻らない現状もお話しされましたが。
三石:現在の人口動態を見ても、18歳から23歳のところが落ち込んでいます。都会に出た子どもの7割以上は戻らない。これが地方創生にとって大いなる問題となっています。
夏になると大学生を受け入れて、フィールドスタディをします。東大、京大をはじめ全国から学生が来るのですが、講座のなかで「卒業したら地元に帰ろうと思う学生は手を挙げて」と尋ねると、偏差値の高い大学に通っている学生ほど手を挙げません。地方創生にとって、本当に一番望ましいことは、その地域出身の学生たちがみんな戻ってくることなんですが。
――そのために必要なことは、何だとお考えですか。
三石:やはり仕事の量と質を高めることです。そして、特徴ある商品の開発、つまりコモディティ化しないものを、地方都市がどのようにつくっていくのか、どのようにブランド化していくのかが鍵になると思います。一方で、ブランド化に必要な人材が流出し、戻らないという状況がありますので、ブランド化には、プロのデザイナーやコピーライターと組む必要があります。
飯田市の場合、精密機器製造の分野では特殊な製品をつくっている会社が結構あります。また、農業に関してはりんごが有名ですし、生産者の名前に由来する稀少和牛もあります。その牛は、畳の上でモーツァルトを聞かせながら、独自の自家製ブレンドの飼料やりんごなども食べさせて、2年以上の時間をかけて飼育する高級和牛です。ただし、このブランド牛は京都の肉屋さんが一手買いしてしまう状況です。
これらの商品のブランド化は、中心市街地を活性化したり、地域全体の“地元愛”を高めたりすることにもつながります。
――そのような活動のなかで、新たな発見もあるとか。
三石:地元で新しい能力が育ったというか、もともと能力があった人材を私たちが発見したことがあります。それぞれの地域には、必ず有能な人材がいるものです。
飯田市の人口は約10万3000人で、近隣の町村を含めても17万人程度の閉鎖商圏です。まちづくりは、ここよりも小さい地域のほうがまとまりやすく、10万人ぐらいが最も難しい規模だと思われます。ですから、ほかの地域からは、飯田市でうまくいけば、これよりも規模が大きくても小さくてもうまくいく、そんな視点で見られていると思います。まちづくりは規模の大きさによって手法もどんどん変化しますので、これからも現在の規模に合った展開を進めていきたいと思っています。
■ ■ ■
プロフィール
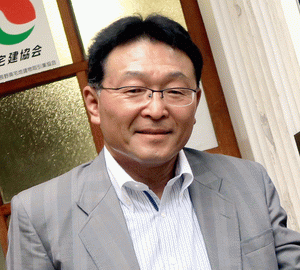
三石 秀樹(みついし・ひでき)
1958年長野県生まれ。1998年株式会社飯田まちづくりカンパニーに入社、1999年取締役事業部長に就任し、現在に至る。2002年NPO法人いいだ応援ネット イデア理事、2011年一般社団法人飯田五平もち楽会理事に就任。同年、国土交通省の全国中心市街地活性化まちづくり連絡会議監事に就任。経済産業省の街元気リーダー、タウンプロデューサー、地域活性化伝道師、NPO法人国際りんご・シードル振興会副理事長、一般社団法人全国タウンマネージャー協会監事も兼務している。
DATA
組織・団体名 株式会社飯田まちづくりカンパニー
住所 〒395-0045 長野県飯田市知久町1丁目10
設立 1998年8月
Webサイト http://machikan.jp
組織図/他組織との連携図
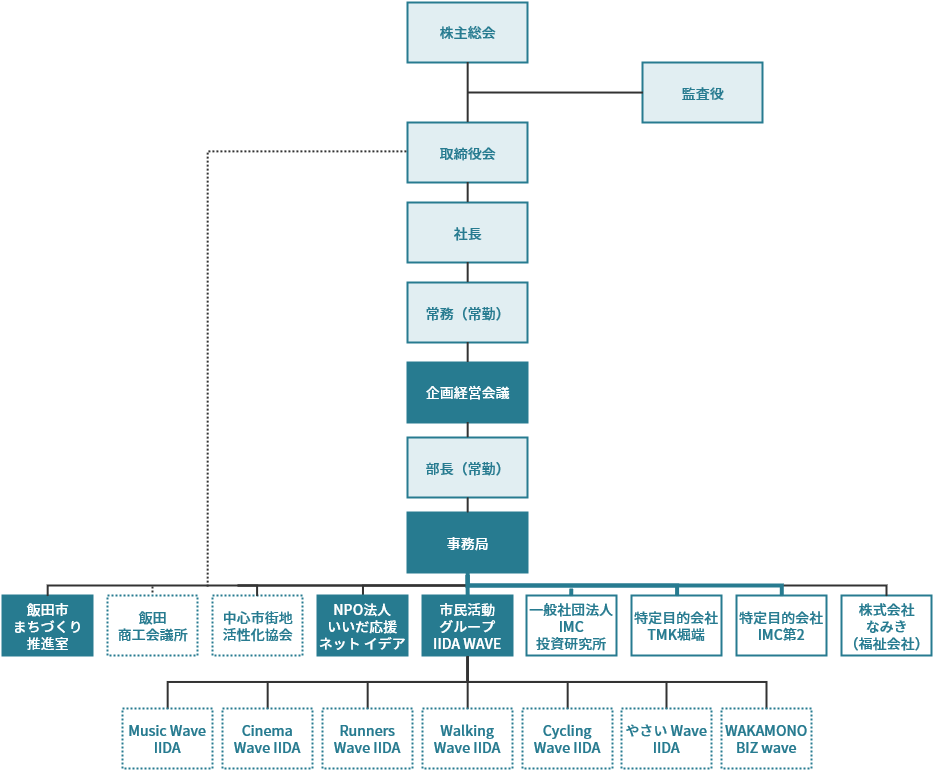

タグ
- 地方創生実践事例
- ローカルブランディング
- 中心市街地活性化
- コラボ
- 地元愛
- 空き家・空き店舗
- 中部地方
関連リンク
シェアする