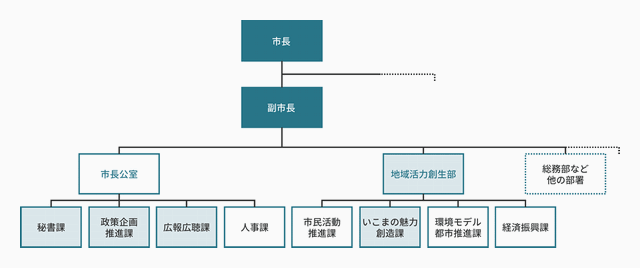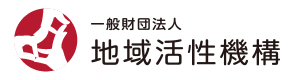就業支援の強化で子育てと仕事を両立できる都市に

奈良県生駒市
生駒市市長公室
政策企画推進課 課長補佐 岡村 匡祐 氏
政策企画推進課 政策企画推進係 係長 日高 興人 氏
大阪のベッドタウンとして発展した奈良県北西部の生駒市は、東洋経済新報社が公表した「住みよさランキング2016」で県内1位、関西10位になるなど魅力ある住宅都市として知られるが、合計特殊出生率は低迷し、転入数も近年は減少傾向にある。生駒市はそれらの課題に対し、出産・育児環境の整備やシティプロモーションのほか、子育て層の女性に対する就業支援策を打ち出し、地道な取り組みを始めている。
主な取り組み
◎テレワーク&インキュベーションセンターの整備
◎ママのプロボノ活動促進事業の開始
◎シネアドによる効果的なシティプロモーション
◎地域活力創生部、いこまの魅力創造課などの新設
◎人材育成基本方針の見直し
◎市職員の採用における公務員試験の廃止とSPIの導入
など
子育て層女性の就業率向上が鍵
――生駒市は「住宅都市としての地方創生のモデルをつくり上げる」ことを目標に掲げていますが、現状の課題を教えてください。
岡村:本市は大阪中心部まで電車で20~30分の住宅都市です。地方創生の推進には、この地理的条件が魅力であり、強みでもあります。人口動態としては、20代後半から30代前半の子育て層の転入が多いという特徴があるのですが、実はこの数年、少しずつ減少しています。また、1人の女性が一生の間に産む子どもの平均数を表す合計特殊出生率は2005年に過去最低の1.17となりました。この年は全国的にも過去最低の1.26でしたが、それよりずっと低い数値だったのです。
しかし一方で、本市の調査では93%の夫婦が子どもを2人以上望んでいることがわかりました。ほしくても持てない理由は「経済的な負担が大きい」が60%と圧倒的で、「育児と仕事との両立ができない」が19%と続きます。
課題は明らかです。子育て層が働きやすいようにするとともに、子育て世帯の経済力を向上させなければなりません。転入数を維持するには、本市の魅力発信も必要でしょう。
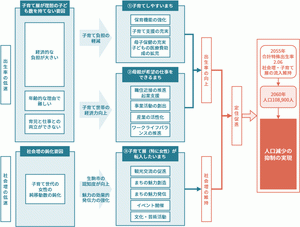
生駒市の取り組み内容と数値目標
――そのためにどのような施策を打ち出されていますか。
岡村:母子保健や医療費助成の充実、保育環境の整備などは当然として、子育て層の女性に対する就業支援を強化しています。というのも、本市は専業主婦率が高い一方で、20~30代の女性は、高等教育を受けた方の割合が非常に高いのです。調査では、就業していない30代女性の85.5%が「収入を得る職業を持ちたい」と答え、39.5%が「子育てと両立できる勤務条件の仕事がない」としています。つまり、就業意欲はあるのに、子育てと両立できる仕事がないと訴えている専業主婦が多いのです。
このような状況の改善に向けて取り組んだことの1つはテレワークで、2017年3月にテレワーク&インキュベーションセンターを整備します。市内で就業できれば、お子さんが保育園で発熱しても、生駒山を越えて大阪から戻るという心理的ストレスがなくなりますし、自分で起業すれば就業時間は柔軟に調整できます。センターについては、主に大阪府下の企業にサテライトオフィスとしてご利用いただけるようお声がけしています。
再就職に向けたウォーミングアップの仕組みも
――テレワークや起業を勧められても、二の足を踏む専業主婦が少なくないのではないでしょうか。
日高:そのような懸念もあり、2016年度の下半期にママのプロボノ活動促進事業というものを始めました。「プロボノ」は、“公益のために”を意味するラテン語の pro bono publico が語源の概念で、専門的な知識やスキルを社会貢献のために、少額ながら有償もしくは無償で提供する活動を指します。つまり、スキルを持ちながら家庭に埋もれているママに、まずはプロボノで働いていただければというわけです。
例えば、市内には、飲食店や小売店などの小さな事業者が数多くいますが、経理が苦手、パソコンが苦手など、それぞれ悩みを抱えています。プロボノ活動促進事業は、それらのニーズとママたちのスキルをマッチングさせる事業で、「イコママボノ」と呼んでいます。
結果として、事業者は悩みを解決でき、ママは自分のスキルが社会に役立つことを再認識し、もう一度働こうと思うようになる。実際の仕事は、再就職に向けたウォーミングアップとスキル維持につながります。一石二鳥の仕組みです。
9月には、第1弾となる「イコママボノ」の説明会が開かれました。これは2016年4月に新設された地域活力創生部の市民活動推進センターららポートが推進しており、今回は市内で活動する3団体の抱える課題を、ママたちのスキルで解決する予定です。
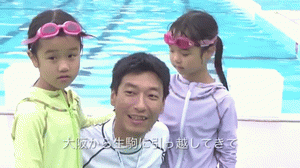
「いこまの魅力創造課」が市民PRチーム「いこまち宣伝部」を組織して製作されたCM。大阪府内にある3つの映画館で、本編上映前に放映された
――子育て層の転入数の維持に関しては、どのような取り組みがありますか。
岡村:市民や市外の人に向けた、市の魅力の発信ですね。この目的で地域活力創生部の「いこまの魅力創造課」がシティプロモーションを推進していますが、肝心なのは“口コミ”です。それには市民のシビックプライドを高める必要があります。また、市外には本市に住んでみたいと思う人を増やさなければなりませんので、その両方を狙い、生駒の魅力を伝えるCMを製作するなどの活動をしています。これをインターネットだけでなく、転入の多い大阪府内の映画館で『妖怪ウォッチ』などの上映前に繰り返し流しています。いわゆるシネアドです。テレビとは違い、必ず集中して見てもらえるので、その効果に期待しています。
公務員試験でなくSPI、スーパー公務員研修も
――市長の意向もあり、自治体内での人材育成方針が見直されたそうですね。
日高:2015年度、人材育成基本方針が改訂されました。今の市長が副市長時代につくったものがもとになっていて、冒頭に「組織にとって最高の宝は『人』です」とあったり、職員に求められる能力の重要な要素に「地域愛」が掲げられていたり、特徴ある表現も印象的です。
岡村:“事業は人なり”と言いますが、これは行政も同じ。立派な組織をつくっても、それを生かすのは人です。新方針に共感しつつ、自分がそれだけの力を身につけられているかと、よく自問するようになりました。
――人材の獲得や研修については、どのような取り組みをされていますか。
日高:採用は知識重視の公務員試験をやめ、SPI(総合適性検査)を導入したほか、面接回数を増やし、面接重視の選考にするなど、民間企業に近い方法に変更しました。優秀な人材を採用し、組織の活性化を図るには、民間志向の方々にも門戸を広げるべきです。2016年度は年齢制限を設けない中途採用も実施しました。
岡村:研修に関しては、採用後3年目までは特に力を入れています。座学だけでなく、外に出てのインタビュー研修やホテルなどの民間企業への派遣研修など、種類も豊富です。最近の試みでは、2016年に「スーパー公務員研修」を実施しています。全国各地で活躍中の公務員をお招きし、ノー残業デーの就業後に講演を聞き、ディスカッションします。初回は、救急医療改革と『県庁そろそろクビですか?』という本で有名な佐賀県庁の円城寺雄介さんに来ていただきました。
全国にも目を向けながら個人と組織の力を高め、街に出て、人々と連携し、創意工夫を重ねていく。そういう基本を忘れず、着実に取り組んでいきます。地域の置かれた状況は厳しいですが、やりがいに満ちています。
■ ■ ■
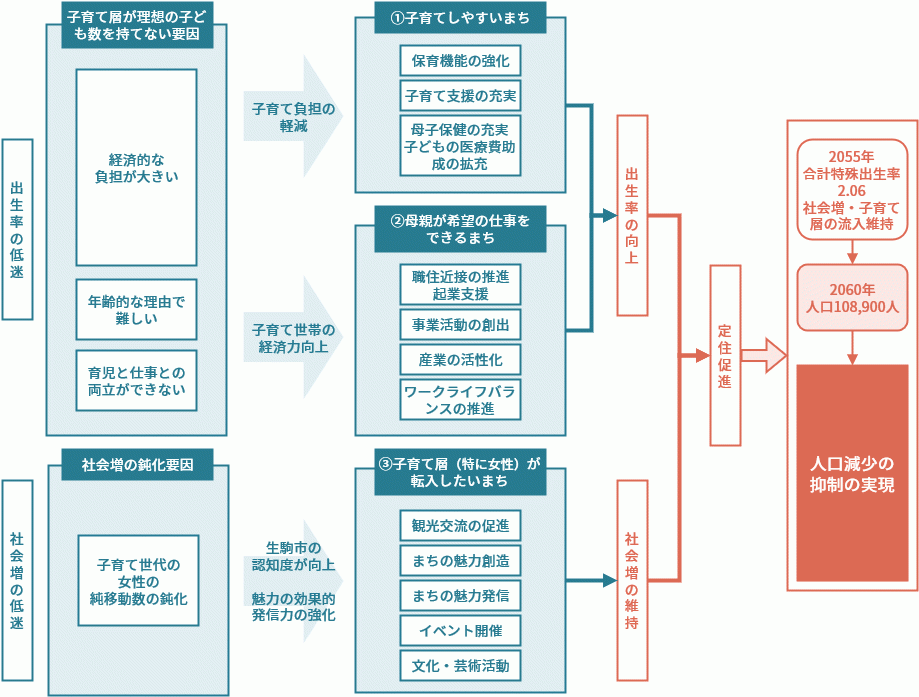
プロフィール

岡村 匡祐(おかむら・きょうすけ)
1994年、生駒市役所入庁。介護保険課主査、企画政策課企画係長などを務め、2016年4月より現職。旧・企画政策課が2016年4月から市長直轄の政策企画推進課となり、市長の特命や重要施策の連携調整を担うほか、総合計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略も担当している。

日高 興人(ひだか・おきと)
2001年、生駒市役所入庁。土木課、財政課副係長などを務め、2016年4月より現職。
DATA
組織・団体名 生駒市市長公室政策企画推進課
住所 〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号
設立 2016年4月
Webサイト http://www.city.ikoma.lg.jp/
組織図